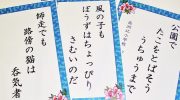私たちが暮らす浦安を歩いてみよう。小さな発見があるかもしれない。第1回は、「原風景を巡る」。風薫る5月、漁師町、浦安の風情が色濃く残る猫実、堀江を探訪した。


旧江戸川がとうとうと流れる。係留された船宿の釣り船が明るい陽光を浴びていた。電車が轟音を響かせ、鉄橋を走って行く。この界隈には昔、定期船(蒸気船)の発着所があり、「蒸気河岸」と呼ばれていた。定期船は東京―浦安―行徳を結び、東京方面へ行商に出かける人々も利用していたという。
昭和初期、浦安で暮らした作家、山本周五郎は名作「青べか物語」で活気に満ちた「蒸気河岸」の情景を生き生きと描いている。昭和15年、浦安橋が開通した。定期船を利用する人は減り、やがて廃止となった。今は、釣り人らが行き交い、多くの市民が散歩やジョギングを楽しんでいる。
境川に沿って歩いていく。ほとりに緑地があった。浦安町役場跡地だ。明治時代、堀江、猫実、当代島の3村が合併して浦安村が誕生。その後、浦安町となった。役場は和洋折せっ衷ちゅうのモダンな建物で、浦安の自慢のひとつだったそうだ。
昭和49年、庁舎が猫実1丁目に移転するまで、この地が行政の中心地だった。往時は、松の大木が翼を広げたように枝を境川に伸ばし、浦安のシンボル的な名木と称えられたという。だが、枯れて、姿を消した。惜しい。
◇

清瀧神社の境内には大木がそびえ立ち、新緑が美しい。老若男女が次々に参拝に訪れる。若い母親は「赤ちゃんが健やかに育ちますように」と願ったという。
本殿は江戸時代に建て替えられた。ケヤキの大木で建築された。精巧華麗な彫刻が施されている。龍や浦島太郎の浮き彫りが見事だ。境内には堀江水準標石が今も残る。明治時代、江戸川や利根川の水位の基準点として設置されたという。
おや、「ゴーン」という鐘の音が響いてきた。どこで鐘をついているのだろうか。
大蓮寺の「時の鐘」だった。副住職の江口直定さんが「午前11時に、11回、鐘をつきます。昔は、漁や農作業をしている人たちに時刻を知らせていたのです」と説明する。
鐘楼の鐘は戦時中、金属供出によって献納された。戦後、多くの檀家が基金を積み立てて再鋳し、時の鐘がよみがえった。いい話ではないか。江口さんは「大晦日には多くの人が列をなし、除夜の鐘をつきます」とにこやかに話した。
さて、昼時だ。フラワー通りの老舗そば処「天哲」ののれんをくぐる。家族で営んでおり、あたたかい雰囲気だ。熱々の海老の天ぷらにかぶりつく。ぷりぷりしている。おいしい。そばをたぐる。うまい。
◇
昼食後、旧江戸川の堤防を東京湾に向かって歩いて行った。堀江ドックが見えてきた。多くの船が係留されている。二人の男性が腰かけて釣り談義。穏やかな情景だ。
さらに足を伸ばす。清瀧弁財天に到着した。創建のいわれが興味深い。
明治時代、1匹の白蛇が松の根元にある穴に入っていくのを住民が目撃した。驚いた住民が行者に伺いをたてると「白蛇は弁財天の使い」と告げられた。そこで祠し 堂どうを建てたという。往時は霊験が知れ渡り、参詣人でにぎわったと伝えられる。境内に清らかな池がある。亀が気持ちよさそうに泳いでいた。
小さな旅の最後に出発地点の猫実にもどった。りっぱな看板が掲げられた「西金」で佃煮を買った。詰め合わせとアナゴ。心地よい一日だった。さて、今夜は自宅でいっぱいやるとするか。